室生犀星作『幼年時代』と
代々木ゼミナールの恩師のお話
狩野香苗
新年明けましておめでとうございます。今年もこのページで懐かしい子ども時代の読み物について、気の向くままアレコレと書かせていただきますので、お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。

◆至れり尽くせりの「21世紀版 少年少女日本文学館」
思えば私が少女時代を過ごした1960年代から70年代は、文学全集が大人気で、私も小中学生の頃は偕成社、講談社、集英社、ポプラ社などから刊行されていた児童文学全集をせっせと読んでいた。文学全集以外のいわゆる単行本の子ども向けの本というのは岩波書店の翻訳本くらいで、現在と比べて極端に少なかったような気がする。
さて、今回は日本の児童文学を読もうと、ネット書店を徘徊して見つけたのが、講談社の「21世紀版 少年少女日本文学館」だ。

全20冊のラインナップは
1たけくらべ ・山椒大夫
2坊ちゃん
3ふるさと・野菊の墓
4小さな王国・海神丸
5小僧の神様・一房の葡萄、他
6トロッコ・鼻
7幼年時代・風立ちぬ
8銀河鉄道の夜
9伊豆の踊子・泣虫小僧、
10走れメロス・山椒魚
11二十四の瞳
12赤いろうそくと人魚
13ごんぎつね・夕鶴
14ビルマの竪琴
15ちいさこべ・山月記
16しろばんば
17母六夜・おじさんの話
18サアカスの馬・童謡
19雪三景・裸の王様
20汚点・春は夜汽車の窓から
全20巻のうち、1巻の樋口一葉『たけくらべ』から14巻の竹山道雄『ビルマの竪琴』までは、まさに私が少女時代に親しんだお話ばかりの、納得のラインナップ。だが、原民喜の『夏の花』が入っていて驚いた15巻から、村上春樹『貧乏な叔母さんの話』『踊る小人』が入っている最後の20巻までは、大岡昇平、安岡章太郎、小川国夫、開高健、野坂昭如など、20歳を過ぎた大人になってから読んだ作家の本ばかりだ。児童文学全集ではなく、あくまで日本文学館というシリーズ名通り、刊行された2009年時点での、少年少女にも読める日本文学が選ばれている。
◆ちょっと長い余談が続きます
この数々の名作の中から、第7巻「幼年時代・風立ちぬ」を選んだのは、室生犀星、佐藤春夫、堀辰雄と、十代後半に熱心に読んだ作家が並んでいることに惹かれたからだ。特に犀星には思い入れがあり、19歳のときには彼の生地の金沢を旅し、近年になっても別荘があった軽井沢でゆかりの場所を訪ねる文学散歩を楽しんだりした。
この文学散歩は軽井沢高原文庫の主催だった。余談になるが、塩沢湖の近くにあるこの文学館の敷地内には、堀辰雄の山荘が移築されている。初めてここを訪れた晩秋の小雨の降る午後、犀星の『我が愛する詩人の傳記』に描かれている立原道造や堀辰雄ら、美しい詩や小説を残して若くして世を去った詩人たちに思いを馳せながら、気分だけは夢見る文学少女になって、この山荘をのぞいた。すると、大昔の百恵友和主演の映画「風立ちぬ」の色あせた大きなポスターが、質素な山荘の壁でパタパタと風にはためいていた。誰やねん、こんなポスターを貼ったのは! あっという間に魔法は解けて、文学少女は毒舌オバハンに戻ってしまった。
前置きが長くなってしまい、なかなか『幼年時代』の話にたどり着かない。しかも、今回はこの物語を読むに至るまでをくどくどと語りたいので、前置き、余談がまだまだ続くことを、お許しください。
前述したように、もっぱら『たけくらべ』や『ビルマの竪琴』などの子ども向きの本を読んでいたのが終わったのは、14歳のときだ。1969年、庄司薫の『赤頭巾ちゃん気をつけて』を読んだのが、大人の本を読むことのきっかけとなった。
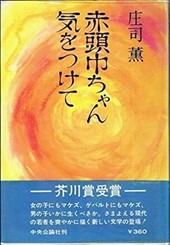
この作品は学生運動の激化で東大入試が中止となったときの、東大を目指す高校3年生のある1日を描いたもので、純文学としてはめずらしくベストセラーとなり、映画化もされたので、中学生の間でも話題となっていた。それは私が初めて読んだ芥川賞受賞作品だったが、なんて読みやすくて面白いんだと、驚いたことをよく覚えている。同書はサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』の翻訳との類似性も指摘されていたので、これも読んでみた。
それからは少しずつ少年少女文学全集から離れていき、文学全集も大人向きの文芸大作を読むようになった。やがて『風と共に去りぬ』に夢中になり、シェークスピア、ヘッセ、ロマン・ロラン、ゾラ、モーパッサン、夏目漱石、芥川龍之介と、手当たり次第に読んでいた中学時代。高校生になると、北杜夫、遠藤周作、井上靖など、当時人気の日本人作家の作品も読むようになった。
本ばかり読んでいたので、当然、学校の成績も現代国語だけはよかったが、古文や漢文はダメで、他の学科はもっとダメダメだった。低迷する成績とそれに反比例するように増える読書量。高校の現代国語の授業は、4月に教科書が配られると1日で全部読んでしまい、授業では特に興味を引くようなこともなく、ひたすら退屈だった。当時の現代文の試験では、大江健三郎の評論が取り上げられることが多かった。そこで、私はひたすら大江健三郎を読んで、それだけで大学受験を乗り切ろうという、バカバカしい作戦まで考えていた。
やがて高校3年の夏がやってきた。さすがの私もこの成績のままだと大学進学はできないとようやく気付き、遅ればせながら代々木ゼミナー(以降「代ゼミ」)の夏期講習会に通うことにした。
◆代ゼミの名物講師、堀木先生
それは2週間くらいの短期講習会で、場所は代ゼミの原宿校だった。ラフォーレができる前の原宿はまだまだ静かな街だったが、横浜から電車に乗って原宿に通うのは当時の高校生にとってはとても刺激的だった。私も受験勉強より当時高校生に大人気だったカジュアルファッションのCABINのバーゲンが原宿であるのが楽しみで、遊び半分で通い始めた。
ところが、この夏期講習会で私は現代文の堀木博禮先生と出会い、多大な影響を受けることになる。当時、先生は代ゼミを代表する看板講師で、東大受験クラスの現代文と小論文を受け持ち、駿台生までが堀木先生の授業にひそかに通っているという噂があった。受験界隈の講師の優劣などまったく知らず、のほほんと原宿とCABINを楽しもうと思っていた私が、夏期講習会で堀木先生の授業を受けられたのは、幸運としかいいようがない。
堀木先生の授業はとてつもなく面白かった。本を読んでいれば、現代文の試験は簡単に解けると思い込んでいた私には、まさに目からうろこのような内容だったのだ。
私はそれまでの読書体験の積み重ねだけを武器に、文章を感覚的にとらえ、解釈していた。作家についての知識は乏しいもので、そのバックグラウンドなど考えたこともなかった。読書好きな高校生レベルなら、特に勉強しなくても、なんとか学校の現国の試験はクリアできる。「例文の主旨を100文字以内で要約せよ」とか「下線部分が意味することはなにか」とか、あとは漢字クイズのようなものばかりだからだ。
しかし、堀木先生は理論的に文体や文脈を解読し、その意味することを文章に書けないと、大学受験どころか、高いレベルでの読書はできないことをわからせてくれた。ただ文字を追い、ストーリーをたどるだけの読書ではだめだと、思い知らされた。クイズのようだとバカにしていた漢字テストさえ、漢字一文字に込められた作者の意図を汲み取るためには、必要不可欠な勉強であることを教えていただいた。
さらに先生は、現代文の作家たちの文学的背景を教えるために、簡単な現代文学史も加えてくださった。それは高校の授業では知ることができない、知的好奇心を満たしてくれる、素晴らしい授業だった。
堀木先生のプロフィールを調べて、代ゼミ以外に都内の女子短大の助教授でもあることを知り、先生の授業をとるために、私はそこを受験した。そして履修した中に、堀木先生の近現代詩の授業があった――お待たせしました、やっと室生犀星にたどり着きました!
堀木先生の近現代詩の講義は、犀星の生い立ちから、その作品を解き明かしていくというものであった。もう半世紀も昔のことで、どんなテキストを使ったのかも詳細は忘れた。ただ、今でも私の本棚には犀星の『我が愛する詩人の傳記』(昭和46年、中央公論社)と現代教養文庫『愛の狩人 室生犀星』(安宅夏夫著、昭和48年、社会思想社)が残っている。特に『愛の狩人 室生犀星』はたくさんの傍線や書き込みがあるので、この文庫本をサブテキストに使ったのかもしれない。

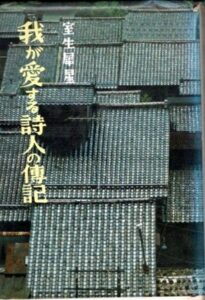
どう見ても、近現代詩よりファッションや放課後の合コンのことで頭がいっぱいであろう、着飾った若い女子学生ばかりの華やかな教室では、堀木先生も代ゼミのときとは違って、なんとなく身構えているようなところがあった。最初に学生を指したときに、「右端の赤いルージュの女!」と言ったのには、驚いた。19歳の私の眼には、なんだか文学青年崩れの荒んだ中年男のように映ってがっかりしたことを、今も鮮明に覚えている。
それにも関わらず、やっぱり代ゼミのときと同じく、その講義は面白かった。
堀木先生の授業は、室生犀星を中心とした近現代詩の講義だったが、犀星の生母と養母について、かなり時間を割いて解説していた。
半世紀前の講義内容の詳細を、『幼年時代』を読み直すまでに思い出すこともなかったのだが、唯一今まで覚えていたのは、犀星の生母の本名のことだ。石川県の貧しい山村に生まれた母は「ステ」と名付けられた。その名前は望まれて生まれた子どもではないことの象徴で、ステのその後の不幸な人生まで予言するような名前である――尊敬する先生の授業で覚えていたのが、「右端の赤いルージュの女!」と犀星の母の名前だけというのはお恥ずかしい限りだが、それだけ強烈な印象となって、私の中で50年間残っていた。
◆詩人室生犀星の原点となる、哀しき幼年時代

犀星は大変複雑で不幸な生い立ちをしている。
生まれてすぐに実の親から寺の住職の内縁の妻に引き渡され、その私生児として育てられた。やがて住職の養子となり室生姓を名乗るが、成績不振と養家の経済的困窮から13歳で高等小学校を中退し、裁判所の給仕として働き始めた。
独学で詩を学び、詩人として頭角をあらわした犀星が、大正8年(1919)30歳のときに「中央公論」に初めて発表した原稿用紙90枚程度の短編が、自伝的小説『幼年時代』だ。故郷金沢を舞台に、犀星が小学校に入学した明治28年6歳頃から、高等小学校を退学する明治35年13歳の間の出来事を描いている。
私は母の顔をみると、すぐに腹のなかで「これが本当のお母さん。自分を生んだおっかさん。」と心のそこでいつも呟いた。
「おっかさんはなぜ僕を今のおうちにやったの。」
「お約束したから。まだそんなことを判らなくてもいいの。」
と、母はいつも答えていたが、私は、なぜ私を母があれほど愛しているにかかわらず他家へやったのか、なぜ自分で育てなかったかということを疑っていた。
『幼年時代』では、幼い犀星は養母の家から近い実家をたびたび訪れ、隠れるように幸福な時を過ごしている。きれいに整頓された清潔な部屋で色白の母にお菓子をねだり、庭木の手入れに精を出す士族の父を手伝い、二人がお茶をしている間にはいって母の膝で居眠りをする少年に、「何も彼も忘れ洗いざらした甘美な一瞬の楽しさ」と言わせている。
しかし現実は、妻を亡くした老齢の男が、家の女中を孕ませた挙句に世間体を憚り、他人の私生児とするために養育費をつけて我が子を手放したのだった。やがて父が亡くなると、たちまち母は家を追い出されて行方不明となってしまう。
養母は気性の荒い人で、養育費を当てに犀星の他にも3人の養い子を育てていたが、子どもたちに愛情を注ぐこともなく、厳しく折檻することもたびたびだったらしい。だが、『幼年時代』の中ではこの養母も「母は叱るときは非常にやかましい人であったが、可愛がる時も可愛がってくれていた。しかし私はなぜだか親しみにくい……」と、かなりソフトに描いている。
不幸な名前をもち、行方不明となって再会もかなわなかった生母と、暴力と暴言で子どもを痛めつける養母。その結果、犀星は強情で粗暴な振る舞いが目立つ少年となった。喧嘩早いため友だちからは敬遠され、教師からは目の敵にされていた。そうした環境の中で、唯一の慰めは優しい義理の姉の存在だけだったが、その姉もやがて嫁いでいなくなる。
私はだんだん自分の親しいものが、この世界から奪られてゆくのを感じた。しまいに魂までが裸にされるような寒さを今は自分の総ての感覚にさえ感じていた。
犀星は生涯で単行本約260冊、詩集約30冊を出版し、内容も詩、小説、随筆、俳句、戯曲、童話、評論と多岐にわたっていて、実に多くの作品を生みだした。それらすべての作品は、小説であれ評論であれ、彼の原点である詩が形式を変えたものであると言われている。そして、生き別れとなった生母への追慕を描き続け、それが昇華して “女人”を描くことが生涯のテーマとなった。
『幼年時代』は小説ではあるが、詩人の繊細な感性があってこそ書き得た小説だと思う。不幸な出自と家庭環境、友だちもできず、教師からは憎まれ、暗く辛い日々が続くばかり――読んでいて苦しくなるような内容なのだが、この粗暴な少年の中の繊細で孤独な傷つきやすい魂に触ると、そこに豊かな詩心が芽生えているのが伝わり、心惹かれる。
二人の母や姉や幼馴染の少女らと過ごす時間の中に、幼いながら密やかなエロティシズムをにじませる、少年の感性の鋭さ。少年同士の喧嘩や、教師への憎しみや抵抗さえ、その愛情を求める切ない思いが伝わり、心が揺さぶられる。
そして詩人らしい美しい日本語に接する喜び。言葉は時代とともに変化していくというが、100年以上前に書かれた小説の中の日本語の言葉の美しさ、表現の豊かさは、残っていてほしい。
この小説は決して児童文学ではないので、今の少年少女が読む機会は少ないのかもしれない。だが、短い子ども時代だけが持つ喜怒哀楽は普遍的だ。いつの時代の少年少女、そしてかつて少年少女だった大人にも、読んでもらいたいと思う。
それにしても、私が遠回りしたけれど編集者になり、子どものころからの“本を作る人”という夢をかなえることができたのは、あの原宿の夏の日に出会った堀木先生の講義のおかげだ。
その後、少子化の中で代ゼミも経営縮小のために講師の大リストラを行った。テレビにも登場する派手なパフォーマンスで知られる若い講師たちがもてはやされるようになり、堀木先生のような地道に積み上げていくオーソドックスな授業は敬遠されていったという。
先生は2001年にお亡くなりになったが、今でも、その著書は優れた現代文の参考書として、読み学び継がれている。

