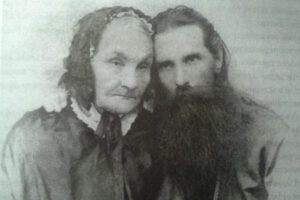「つとめを果たす(2)―『僧正』」
渡辺聡子
題名
「僧正」は、仏教の高僧を表わす言葉ですが、ロシア語の原題は «Архиерей» (アルヒエレイ)、正教の位階最高位に位置する主教職をさし、主人公の副主教ピョートル(修道名)もその一員です。1902年、チェーホフの死の2年前に書かれたこの作品は、主人公が復活祭を目前にして亡くなるまでの1週間をたどりますが、作者の自伝的要素を影のように織り込みつつ、人生と死を、永続的な時間や大きな世界において見た作品でもあります。
アルヒエレイのつとめ
復活祭を控えた4月初め、戸外は日に日に春の息吹に満ちていきます。明るい陽ざしに木々は目覚め、小川はせせらぎ、野原からはヒバリの歌が届き始めます。一方ピョートルは、自分が腸チフスに罹っているとも知らず、日を追って具合が悪くなっていきます。熱や身体の痛みをおしてふだんの仕事以上に、イエスの受難をたどる聖週間の特別な儀式を執り行い、病床にある主教の職務を代行し、休む間もなく働きます。
副主教には、なるべくしてなったのではありませんでした。補祭の子に生まれたものの、パッとしないので丁稚奉公に出されかけた少年が、神学校、神学大学へと進み、難しい論文を書いて32歳で神学校の校長となり、大修道院長の資格も得ます。前途洋々かと思った時に病を得、全てを捨てて外国に療養に行かねばなりませんでした。でも、その8年間は、現地の教会に奉仕しつつ恵まれた環境で静かに勉強できたのでした。そして、呼び戻され、副主教に任ぜられたというわけです。

もともと素朴な人で、かつて故郷の村でイコンを掲げた十字架行列の後を、稚い信仰に胸をふくらませ裸足でついて行った少年パヴルーシャ(本名)の心が残っています。聖歌や鐘の音を聴く時に、一番心が慰められるのでした。
けれども、「アルヒエレイ」になってみると、その権威が人々に恐怖を与え、請願者はもちろん年配の長司祭たちまで怯えてひれ伏します。それはピョートルを戸惑わせ、時には苛立たせました。心を割って話せる人が一人もいない孤独と任務の重圧があり、「わたしには主教職など似合わない。いっそ田舎の司祭か堂守のほうがよかった… それとも平の修道士の方が… 」と本音をもらすことになります。
夢かうつつか不思議なできごと
作品の冒頭、修道院の聖堂では「柳の日曜日」の徹夜祷が進んでいます。イエスがエルサレムに入城した時、民衆がシュロを手に歓迎したことにちなんで、この日ロシアでは信者にネコヤナギの枝が配られます。

ろうそくの灯がゆらめく薄暗い堂内に聖歌の朗唱や合唱が響き、ピョートルから小枝を受けとる人々が際限なく現れて波のように揺れています。体調がすぐれない彼にはその老若男女の顔がみな一様に見えるのですが、ふとその中に、もう9年間会っていない母親の顔が見えたような気がします。善良な微笑みをたたえ、小枝を受けとって再び人波にまぎれてしまうまで、その眼は嬉しそうに彼の方に注がれていました。
ふいに、ピョートルの頬を涙が伝い、心を満たされて静かに泣きます。それは近くの人から人へと伝わって、いっとき静かなすすり泣きが聖堂を満たし、おさまります。何が起きたのか、まるで愛が密やかな働きをしたかのような不思議な余韻を残す導入部です。
喜びと落胆
母親は、ほんとうに孫娘のカーチャを連れて田舎から出てきていたのでした。娘婿が死んで、娘と孫が物乞いでもするほかなくなったので、援助を頼みに来たのです。来訪を告げられたピョートルは、再会を待ちかねて胸を弾ませますが、期待は大きく裏切られます。
母親もまた、アルヒエレイになった息子を前にすると、田舎補祭の寡婦の身が憚られて、どうしていいかわからないのです。ピョートルが彼女の肩や手をなでながら、「外国でもどんなに会いたかったことか」と語りかけると、ぱっと顔を輝かせるものの、すぐ真面目な表情になって「ありがたいことでございます」と畏まります。聖堂で見せた優しい素朴な愛が、固い殻を被ったかのように。
その後も彼女は、具合の悪そうな息子を案じつつ、はかばかしく口もきけません。ピョートルは無邪気なカーチャから事情を知り、「復活祭が来たら」と援助を約束したのでした。

最期の幻
木曜日の晩、ピョートルは最後の力をふり絞って、4時間に及ぶ聖大金曜日の儀式を執り行いますが(教会歴では一日が前日の日没から始まる)、その後出血が始まり、手遅れの腸チフスと判明します。その時には見る影もなくやつれて、小さく縮んだような姿になっていました。自分でも「誰よりもみすぼらしくて弱い、小さな存在」であるのを感じ、「今まであったもの全てが遠くへ去っていった」ような気がします。
ここで思い出されるのは、長らく肺結核に苦しみ、最後は腸結核で亡くなったチェーホフが、ちょうどこの年(1902年)大病をした妻の看病に疲れ、休養のため富豪の領地に招かれた時のことです。隣室に泊まった鉱山大学の学生はチェーホフのひどい咳を心配していましたが、雷雨にみまわれた夜中、異様な気配に覗いてみると、チェーホフが呻き、痙攣しながら激しく喀血していたというのです。その大きな眼は、涙を湛えて子供のように頼りなげだったと回想しています。
チェーホフは学生を起こしてしまったことを詫びたそうですが、おそらく母親と暮らすヤルタの家でもこのようなことはあり、彼は母親を心配させないようにひとりで耐えたと思われます。ピョートルの苦しさと弱さの自覚は、チェーホフ自身の体験でもあったのではないかと思います。
しかしピョートルは、この状況を「ああ、いい具合だ… 上等だ」と感じるのです。驚愕した母親が、「パヴルーシャ、息子や、どうしたんじゃ、返事をおし!」と呼びかける中、彼は素晴らしい幻を見ます。それは、自分が「何も持たないただの人となって、杖をつきながら、軽やかに楽しげに野をゆく姿」でした。「頭上には陽光あふれる空が広がり、今や鳥のように自由」なのでした。

全ての煩いから解放されたことが分かる、羨ましいような幻です。でも、この幻は、誰にでも訪れるものではないでしょう。
前回の「つとめを果たす」で、チェーホフ自身を連想させる人物として村の医療に献身するアーストロフ(『ワーニャおじさん』)に触れましたが、この医師は現実との闘いに疲れ果てて、作者よりもうんとシニカルです。この世で報われることはとうに諦め、自分たちがそのために道を切り拓いているはずの未来の人々からの感謝にも、きわめて懐疑的です。彼に残された希望は「もしかすると、死に際に心地よい幻が訪れてくれるかもしれない」ということだけでした。
私は今まで、ピョートルが苦悩しつつも驕ることなく誠実に生き抜いたからこそ、作者からそのような幻を贈られたのだと思っていました。でも、今回読み返していて、もう少し深い意味がこめられているような気がしてきました。
時代の苦悩
ピョートルは際立ったヒーローではなく、大事なことを悟ったわけでもなく、いわばふつうの人です。でも、そんな彼が味わった孤独や哀しみや重圧は、本人は気づいていませんが、時代がもたらした不幸でもあります。
権威の前で卑屈になることや、地位や名声が独り歩きすること、人間同士心を開いて向き合うことの難しさは、帝政ロシアに限ったことではありません。けれども、人々が自分の尊厳に気づきようもないような貧困と蒙昧の内にあること、服従を強いる仕組みが、目立たぬ形で書き込まれていると思うのです。
物乞いと隣り合わせの貧しさがあり、「うわばみデミヤン」と呼ばれる故郷の大酒飲みの神父さんや、やはり酒飲みで、教養があるつもりの先生など、軽い可笑しさにくるんで村の後進性が描かれています。外国暮らしを経たピョートルの眼には、管区の住民はやましいことでもしたかのようにすくみ、請願の中身はお粗末で、神学校の生徒や先生も無知で野蛮にさえ見えます。
傍らにいる修道司祭は、「日本人はモンテネグロ人と同じ民族で共にトルコの軛のもとにあった」などとピョートルの母親に教え、苦しげなピョートルを見ても、蠟燭の脂や、酢とウォッカを混ぜたものを塗ることしか思いつきません。手遅れになって初めて修道院付きの医者(町にいる)が呼ばれ、死に際には3人もの医者が来て立ち合い診察をして去るというおまけがつきます。
また、夥しい書類のやりとりも彼を疲弊させました。たとえば、担当者が管区の司祭全員の操行点を妻子の分までつけることになっていて、それをめぐって「話をし、堅苦しい書類を読んだり、書いたりしなければならなかった」と書かれています。ナンセンスな書類というニュアンスで書かれていますが、聖職界にも皇帝に従う何段階かの監督機関があり、監視体制ができあがっていました。評価される側が戦々恐々だったことは容易に想像でき、どの段階でも賄賂が横行したと言われています。ピョートルの所へ田舎からやって来て、ひと言も話せず帰っていった司祭の老妻も、なにかそうした件で直訴をしたかったのかもしれません。
チェーホフは革命的気運の高まりの中でますます強化される検閲を考慮し、神経を使ってこの作品を書いていますが、長司祭達さえ「がばとひれ伏す」のは、行き過ぎた畏敬というより、アルヒエレイの管理監督権を現実的に恐れたからとも考えられます。『箱に入った男』(1898)では、監視社会に怯える教師が、当局の意向を忖度しすぎて神経がもたなくなっていく様を描いています。ピョートルの重圧は、書類の量もさることながら、望まずしてそうした体制に組み込まれているストレスもあったのではないでしょうか。
人々が自分を卑しくすることにも、「アルヒエレイ」に付与された権力にも慣れることのできなかったピョートルは、帝政ロシアの社会制度がもたらす不幸を人間らしく苦しんだとも言えます。意識を失う前に、「死んでもいいからここを脱出して外国へ行きたい!」という強い衝動にかられています。最期の幻は、時代の重荷を誠実に背負い、新しい社会を見ることなく逝くピョートルに贈られた「解放」だったのではないかと思うのです。
復活祭の喜びと人の一生
ピョートルが亡くなった翌日は復活祭で、一点の曇りもない晴れやかな自然と、喜びにあふれる街のようすが描かれます。
「町には42の教会と6つの修道院があった。喜ばしい鐘の音が朝から晩まで途切れることなく上空に響きわたり、春の大気を揺るがしていた。鳥たちがさえずり、陽は明るく輝いている。市の立つ大きな広場は人で賑わい、ブランコが揺れ、手回しオルガンが鳴り、アコーディオンが甲高い音をたて<……>ひと言で言うと愉快この上なく、万事申し分なかった。去年と少しも変わらず、そしておそらくこれからもそうであるように」
ピョートルの生死に目もくれず、自然は甦り、人々は幸せに酔い、その営みは変わることなく繰り返されていきます。けれども、ここに嘆かわしさはありません。私には、この喜ばしい大気の中に、ピョートルの痕跡が陽に輝く塵となって消えて行ったような感覚があります。
ひと月経って新しい副主教が任命されると、ピョートルのことはすっかり忘れられ、田舎で暮らす母親だけが、たまにアルヒエレイになった息子のことをおずおず話してみるものの、皆が信じてくれるわけではなかった、と結ばれています。
あまりに早い忘却ですが、チェーホフは自分についても、親交のあった作家ブーニンに「僕が読まれるのはあと7年、生きられるのは6年」と語ったそうです。
ピョートルは40を過ぎたあたり、44歳で亡くなったチェーホフとほぼ同年齢です。母親像や、経歴、病と孤独、放浪の夢など、作者と微妙に重なるところがたくさんありますが、予感していた新しいロシアを自分もまた見ることはないということもわかっていたと思います。

ピョートルは、何かが違えばもっと生きられたのかもしれません。そして、心のどこかでずっと望んでいた「一番大事なもの」はわからないまま、カーチャ親子の援助も果たせないままで終わりました。けれども、人生は偶然の組合わせに満ちていて、死はいつも途中切れであることも、チェーホフの死生観の中にあったのではないかと思います。
めぐり合わせた時代と場所で、誠実に力を尽して消える ― それでいい、という声がここでも聞こえるような気がします。
付録