暑く厳しい夏でしたね!
気候も世界状況もますます酷くなっていくこの頃、皆さまはご無事でお元気にお過ごしでしたでしょうか?
“「大きな木の家第6号」をお届けします。” の続きを読む
もうひとつの故郷フローレス 五の巻
モンテイロさんの時間
青木恵理子
1970年代、人類学者がフィールドワークの最中に現地特有の病気に罹り、亡くなることはそれほど稀ではなかった。私がマラリアに罹ってかなり重篤になっても回復できたのは、モンテイロさんと彼の家族の力が大きい。 “もうひとつの故郷フローレス 五の巻” の続きを読む
世界の彷徨い方 2
【フェイルーズの大地】 エジプト/シナイ半島
中村小夜(Saya)
その半島はフェイルーズの大地と呼ばれていた。「フェイルーズ」――アラビア語でトルコ石。深い青色をしたこの石は、透明感もなく光沢もない。しかし、その鮮やかな青の中には、かつて砂漠のベドウィンたちが思いをよせたオアシスが封じ込められているのかもしれない。
“世界の彷徨い方 2” の続きを読む
チェーホフの言葉 第3回
「何もかも分かるようにはできていない」
~『谷間』~
渡辺聡子
今回取り上げるのは、『谷間』(1900)という作品に登場する老人の言葉です。最下層に生きる人々の優しさや、厳しい人生を通して培われた知恵に励まされます。
“チェーホフの言葉 第3回 ” の続きを読む
エレナ・ポーター作『少女パレアナ』
大人が読む少年少女世界文学全集 第6巻
狩野香苗
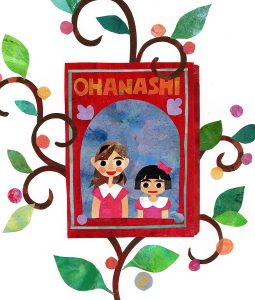
◆記憶はあてにならない……
今回ご紹介する『少女パレアナ』は、私が子ども時代に一番影響を受けた本であり、大好きなお話だったので、約45年ぶりに読み直すのをとても楽しみにしていた。
“エレナ・ポーター作『少女パレアナ』” の続きを読む
猫とかぼちゃ~伝承こぼればなし
桑山ひろ子
「暑い! 外出はやめたやめた!」と家にとじこもっているうちに、早いものでもう9月半ばだ。天気予報によると、まだまだこの暑さは続くという。昔の感覚から言えばとうに秋なのだが、ぎりぎり滑り込みで納涼譚はどうだろう。
“猫とかぼちゃ~伝承こぼればなし” の続きを読む
おとうと
片山ふえ
わたしは末っ子である。
それも、姉たちとは10歳ほども年がはなれた「すごぶるつきの末っ子」なので、わたしがいくら馬鹿なことをしても、家族は「仕方ないよね、ふーちゃんは小さいんだから……」と笑っていた。「ホメラレモセズ クニモサレズ サウイフモノニ ワタシハナリタイ……」と書いたのは賢治さんだったが、わたしはまさに「ホメラレモセズ クニモサレズ」、末っ子の座にのうのうと安住して育った。
“おとうと” の続きを読む
ユーラシア放浪 ⑥イタリア・オーストリア
畔上 明
半世紀昔の旅日記を読み返しているうちに、更にそれよりも10年さかのぼった10代半ばの中学生時代の記憶が蘇えってきました。
0.999…という小数点以下の9が永遠に続く数字を考えると、1との差がどれほどになるかマイナスしてみたならば0.000…と小数点以下の0が無限に続くことになります。果てしない数の連なり0.999…が結果的にはイコール1となることに気が付き、1という数字が永遠と隣合わせにあると感じ入ったものでした。それからというものの、無限という考えに憑りつかれるようになった思春期の思い出です。
“ユーラシア放浪 ⑥イタリア・オーストリア” の続きを読む
PHOTO 哲学の道
片山通夫
京都・東山のふもとの、若王子神社と銀閣寺を結ぶ「哲学の道」。京都大学が近く、かつて西田幾多郎博士らがここを散策しながら思索にふけったから、この呼び名がついたと言われる。昨年、秋が深まりゆくころに、この道を撮った。桜や紅葉のころには人があふれる小道も、おちついた貌を見せていた。 “PHOTO 哲学の道” の続きを読む
