「百」という数には、なにかこう、99までとは違った重みがありますね。「百人力」とか「百戦錬磨」と言えば力強いし、「百薬の長」といえばいかにも身体によさそうだし(笑)、「名を百代に残す」のはなかなか出来ることではありません。(もっとも、最近はちょくちょく「百条委員会」なんていうのも耳にしますが……。)
なぜこんなことを書くかと言えば、「ムーザサロン」が先日めでたく百回目を迎えたからです。 “「ムーザサロン」のこと” の続きを読む
チェーホフの言葉 第1回
チェーホフの連載を始めるにあたって
渡辺聡子
この度、ふえさんの大きな木の家に招んでいただき、嬉しく思っています。
私は長年チェーホフを愛読してきましたが、歳を重ねることや、何かの体験をきっかけに、あらためてチェーホフの作品や生き方の奥深さを知ることがあります。そのことをここでお話しできたらと思っています。初回は長くなってしまいましたが、どうぞよろしくお付き合いください。 “チェーホフの言葉 第1回” の続きを読む
バーネット作『秘密の花園』
大人が読む少年少女世界文学全集 第4巻
狩野香苗
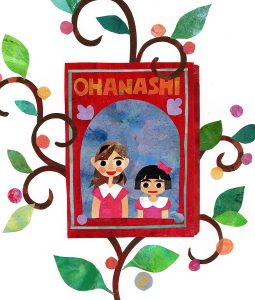
◆まったく読んでいないのに、読んだ気になっている本
いままでここで取り上げた3冊の本には、それぞれ自分なりのこだわりがある本だった。
『飛ぶ教室』は夢中で読んだのに60年たって内容をすっかり忘れてしまった本『十五少年漂流記』は読書の喜びに目覚めて何度も繰り返し読んだ本
『あしながおじさん』は本より舞台の印象ばかり残っている本
いずれも抄訳でなく完訳をしっかり読んだし、子ども心に大きな印象と影響を与えてくれた、忘れられない本だった。
ところが、今回のバーネット(Frances Eliza Hodgson Burnett, 1849年~1924年)作『秘密の花園(The Secret Garden)』は、まったく読んだことがないのに、すっかり読んだ気になっているという、ちょっと問題のある本なのだ。
“バーネット作『秘密の花園』” の続きを読む
吉水法子の貼り絵の部屋
十二支の話
桑山ひろ子
あけまして おめでとうございます。
今年は、再生や永遠を表す、と言われている蛇年ですね!
わたしは、昨年ついに後期高齢者の仲間入り。これを機会に、古い皮を脱ぎ捨て、新しい「わたし」で前進しようと思います。
さて、年の初めは「干支」の話からいきましょう。
日本でよく語られる十二支の動物の順番が決まるお話です。
“十二支の話 ” の続きを読む
シベリアっ子の手記
アントン・ミルチャ
原文のロシア語は、訳文のあとにあります。
日本で初対面の人に「どこから来ましたか」と聞かれて、ボクがロシアだと答えると、それに対する反応はほとんどの場合、「寒いでしょうね」だ。 そこでボクは、ロシアは広い国だからいろんな気候帯がある(そう、日本と同じように)と説明を始めるのだが、そのあとで結局、実はシベリア出身でそこはとても寒い土地なのだと認めるのだ。 “シベリアっ子の手記” の続きを読む
「ユーラシア放浪」4ハンガリー
ハンガリーの友人たちの思い出
畔上 明
日本を離れて6週目となる1976年4月30日、ハンガリーに入国しました。
ハンガリーは、9世紀にウラル語族の遊牧民マジャル人が東欧スラヴ圏中央部の平原に割込むように移り住んで成立した国。現在の国土は日本の4分の1という小国ながらヨーロッパの臍ともいえる場所を占めています。 “「ユーラシア放浪」4ハンガリー” の続きを読む
「片山通夫80歳 大阪を撮る」
これまで「リアリズム写真」を目指していた。その考えのもと、様々な所で様々な写真を撮ってきた。一昨年に出版した写真集『ONCE UPON a TIME』はその集大成だ。
ただ我ながら不満なのは、それらの写真が、額に入れて飾ろうという気にはならない代物だということだ。それで、「新しい作風」と言うといささか面はゆいが「アートとしての写真」に挑戦することにした。
その成果を問う写真展を今日から5月15日まで開く。会場は「大きな木の家」と同じところにある「Gallery遊」。 “「片山通夫80歳 大阪を撮る」” の続きを読む
あるピアノのはなし(「We Love遊」96号)
この拙文は、季刊冊子「We Love 遊」96号(2022年7月刊)に掲載したものです。 “あるピアノのはなし(「We Love遊」96号)” の続きを読む
2025年片山通夫カレンダー
2025年のカレンダーが出来上がりました。写真をいくつか見ていただきましょう。今回のテーマは「出雲」です。ご希望の方は、fue.katayama@gmail.com まで。A4判モノクロ写真13枚 1000円+送料 です。
「大きな木の家」第3号をお届けします。
「大きな木の家」の秋号をお届けします。
暑い暑い夏でしたね。
そして9月半ばの今も、まだ猛暑のような日々が続いています。日本をとりまく環境はますます暮らしにくくなっているようですね。
でも、そんな中でも、ひとときをご一緒に過ごせたら嬉しい、そう思ってまた「大きな木の家」の扉を開けてお待ちします。 “「大きな木の家」第3号をお届けします。” の続きを読む
ウクライナで出版された本『ひらかたゆ……』
片山ふえ
ひらかたゆ 笛吹きのぼる近江のや
毛野(けな)のわくごい
笛吹きのぼる
日本書紀に出てくるこの古歌が、私の「ふえ」という名前の源であることは、「We Love遊」に書いたことが2度あるので、覚えていてくださる方があるかもしれません。
(6号に掲載した「ひらかたゆ……」はこちらでご覧いただけます)。
実は先ごろウクライナのキーウで一冊の日本紀行文が出版されました。その本の題名は “Японія. З хіракати під голос флейти… “これを訳すと、なんと『日本 / 枚方ゆ笛ふきのぼる……』なのです! “ウクライナで出版された本『ひらかたゆ……』” の続きを読む


